企業の研究職は、大学みたいに論文を書いたりするのか?
うちの会社は論文書く人ほとんどいないけど、他社はどうなのだろう?
就活生や現役研究職の皆様、一度は気になったことはありませんか?
研究成果を報告する方法の一つとして、学術論文を投稿して世に公開するという方法があります。
大学などのアカデミアにおいては、良い研究成果を論文として公開し、知見を広く知ってもらうことが一つの使命です。
一方で、その考え方は企業では当てはまらない側面もあります。
民間企業は「営利を追求すること」が優先順位の高い使命であり、それは所属する研究員にとっても同じ価値観が求められます。
そのため、
「論文を書くことが、会社の利益につながらない」
と会社側から判断されると、論文を書くことを後回しにさせられる or 許可されないという状況になってしまうこともあります。
アカデミアと企業では、学術論文に対する考え方が異なると思ってよいでしょう。
この違いについては、以下にまとめています。
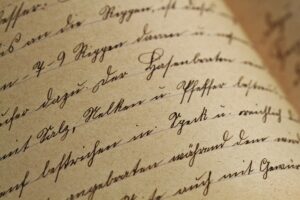
一方で、
「論文を書くことが会社のためになるか」
ということに対しては、会社ごとに考え方が大きく異なると思われます。
論文に対する会社の考え方が肯定的であれば、手を挙げれば論文を書ける環境になっているかもしれません。
そこで、会社ごとにスタンスの違いを大まかに把握するために、
本ブログの著者のツイッターアカウントを使用して企業研究職の皆様にアンケートを取り、
「企業研究職は論文を書けるのか?」について調査しました。
以下のリンクから、私のアカウントを見ることができます。
(ぜひフォローをお願いします!)
今回は、
「企業研究職は、論文を書けるのか?」
という内容で、ツイッターアンケートの結果をまとめました。
企業研究職は論文を書けるのか?
論文を書いたことがある人の割合
まずは、
「筆頭著者で論文を書いたことがあるか?」について聞き取りました。
この質問では、
学生時代と入社後、どちらのタイミングかは分かりませんが、
論文執筆経験者がどのくらいいるかを把握する目的で、聞き取っています。
結果はこちら↓
約半数の方が、筆頭で論文を書いたことがあると回答されました。
学生時代・入社後のどちらのタイミングで執筆したかは分かりませんが、
論文執筆経験者はそれなりにいるようですね。
ちなみに、以前
「企業研究職の中の博士卒の割合」を調べたことがあり、その結果を参考にすると
約20%が博士卒であることが想定されます。
これらの結果を踏まえると、修士時代もしくは入社後に論文を執筆した研究員が一定数いることが想定されますね。
会社の研究成果で論文を書いたことがあるか?
次に、
「会社の研究成果で論文を書いたことがあるか?」
について聞き取りました。
この質問では、筆頭著者としてだけでなく、共著者として参加した経験についても、併せて聞き取りました。
結果はこちら↓
「ない」と答えた方が約半数いる一方で、
「筆頭で書いたことがある」も約30%いるという結果になりました。
数値はともかく、企業の研究成果で論文を書くことができる会社が一定数あることが、
この結果から分かってきました。この点は少し安心ですね。
論文を書ける研究者が所属している会社の方が、
研究に対する基礎がしっかり固まっている研究員が多く、質の高い研究が進められる傾向があるかもしれませんね。
論文を書くことに対して会社は肯定的?評価してくれる?
冒頭で書きましたが、企業は営利活動が目的です。
そのため、
会社の研究成果で論文を書きたいと思っても、会社から企業の利益にならないと判断されると、書くことを認めてもらえないこともあります。
一方で、実際論文投稿している民間企業はたくさんありますし、その内訳は大企業から中小企業まで様々です。
この状況から推察するに、
「論文を投稿することに対する考え方・価値観」
が会社ごとに大きく異なることが想像されます。
そこで、
「ご自身の会社では、論文を書くことについて肯定的か?」
という内容でアンケートを取りました。
結果はこちら↓
論文を書くことに理解がある会社がそれなりにあり、その点については個人的にも安心しました。
一方で、論文を書くことに否定的なスタンスを取る会社も一定数存在するようですね。
特に、
「論文は会社のためにならない」
という考え方が染みついている会社では、論文を投稿・受理させることを、個人の業績として全く評価しないということもあるそうです。
研究職なのに、論文を書くことが評価の対象とならないなんて、特に学生の方にはイメージがわきにくいのではないでしょうか。
ところが、今回のツイッターアンケートの結果を見ると本当にそんな会社は存在するようです。
次に、ツイッターアンケートを使って
「論文を投稿・受理させることは、個人のプラス評価となるか」
というアンケートを取り、論文が評価されない会社の割合を調べてみました。
結果はこちら↓
「論文が成果として評価される」という回答は40%未満にとどまり、
残り60%は「評価されない」もしくは「状況・内容による」となりました。
企業では論文そのものはゴールにはならず、論文を書いても会社のためにならない、
会社の利益につながる論文についてのみ評価する
というスタンスの会社が一定数存在することが分かりますね。
会社の役に立たない論文を書く人はいないと思いますが、それでも、論文を出すことやその内容に対して厳しい判断をしている会社は存在するようですね。
論文投稿には会社の承認が必要
このように、会社によって価値観が分かれる学術論文ですが、投稿すること自体に会社の許可が必要なことは各社共通のようです。
実際に、
「会社の研究成果で論文を投稿する時、承認は必要か」
という内容でアンケートを取ったところ、
90%以上の会社で承認が必要なことが分かりました。
一方で、承認が必要なことはほぼすべての会社で共通であっても、
その中身(何人の承認が必要か?決裁者は誰か?、など)には、各社大きな違いがあると想像されます。
論文を投稿するための承認を得る工程についても、会社ごとにどのように違いがあるか気になりますね。
機会を見て、アンケートを取りたいと思います。
著者の意見:論文を書けるなら書いた方がよい
私の意見ですが、
「論文を書けるなら書いた方がよい」と思っています。
今後、研究職も一つの会社で勤め上げることは難しくなり、転職を含めたキャリア形成が必要となってきます。
特に転職活動をする際には、提出する職務経歴書に「業績」を書く必要があります。
研究職の業績は、「論文」と「特許」が2台巨頭であり、
この2つが充実した職務経歴書であるほうが、高い評価を受けやすいのは間違いありません。
時間がない・会社が許可しないなどの苦労はあると思いますが、
チャンスを狙ってつかみ、論文を出すことをお勧めします。
論文執筆を狙うタイミングは、
「関連特許を出願し終わった直後」が最適です。
これについては、後日記事にしたいと思います。
実際、このブログの執筆者である私もこの方法を使い、
会社の研究成果で筆頭・共著含めて10報以上の論文を投稿しました。
結果、職務経歴書の業績欄もしっかり埋まり、
書類選考を優位に進める一つの要素になったと考えています。
詳しくは、以下の記事にまとめました。

まとめ
・筆頭論文を持っている企業研究員は、一定数いる。
・論文を投稿・受理させることが、企業では必ずしも評価の対象とはならない。
・論文を投稿する前に、会社の承認が必要。
企業研究職の人が論文を書く場合、論文に対する会社の価値観や、会社に役立つ内容で論文を書けるかどうかが大きく影響します。
加えて、会社によっては、論文を書くことをプラス評価に加えてもらえない可能性もあります。
そのような中でも、
皆様にはぜひ論文を書いてもらいたいと思います。
ご自身の今後のキャリア形成に確実に役に立つはずです。
研究者の業績についてもエージェントに聞いてみよう
「本当に論文の業績があった方が、転職で有利なの?」
と気になった方は、一度転職エージェントに聞いてみることをお勧めします。
私は、以下2つの転職エージェント・サイトを主に使用しました。
利用料は一切かかりませんので、
以下のリンクから登録して一度お話を聞いてみてください。
(高年収のハイクラス転職を目指したい方)
(大学院卒の強みを生かした転職に特化)
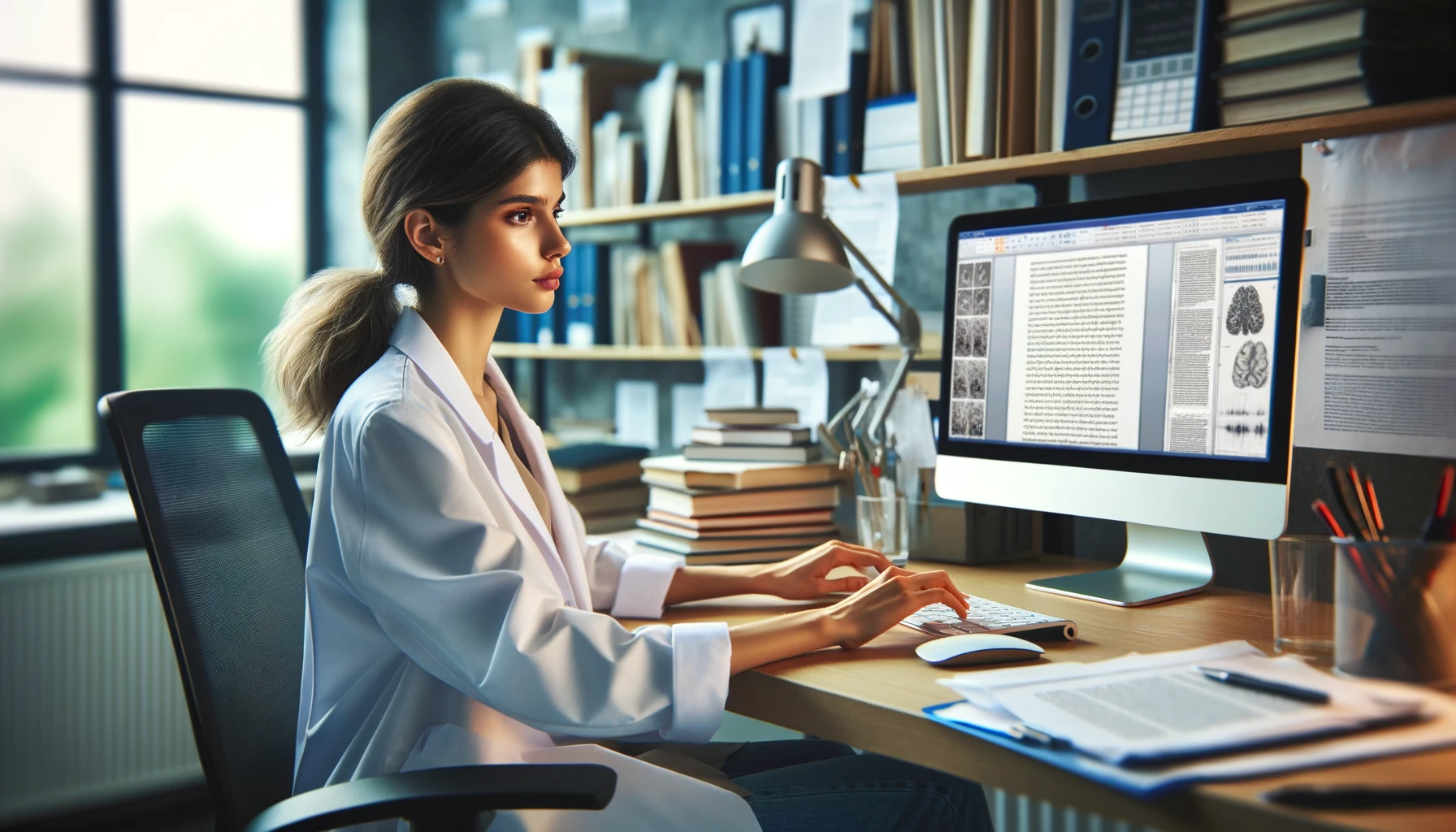








コメント