就職活動は数十年前からの毎年のイベントであり、
多くの学生が毎年その戦いに挑んでいます。
理系学生に関しても同様で、
毎年多くの学生が就活に挑み、笑いあり涙ありの時期を過ごしています。
そんな就活ですが、年ごとの傾向・流行・ルール変更などが重なり、
学生側の就活の進め方も年々少しずつ変わってきています。
理系学生の就活スタイルも毎年少しずつ変わってきており、
現役学生と卒業生(以前の就活生)では、就活の進め方が全然違うようです。
「応募数って今と昔で違う?」
「研究開発職って今も昔も人気?」
「インターンシップって最近は主流だけど昔は?」
この辺りを調べてみることで理系の就活状況の移り変わりが分かり、
「もしかして、就活は昔より最近の方が大変?」といったことも分かってくるかもしれません。
そこで
本ブログの著者のツイッターアカウントを使用して、
企業研究職の皆様や現役学生の皆様にアンケートを取り、
「理系就活の進め方」について調査しました。
以下のリンクから、私のアカウントを見ることができます。
(ぜひフォローをお願いします!)
今回は、
「理系就活の今昔:最近の理系の就活は昔よりきつい?研究職の皆様に聞きました。」
というテーマで、
アンケートの結果を紹介していきます。
最近の理系の就活は昔よりきつい?研究職の皆様に聞きました。
今回のツイッターアンケートでは、
理系学生と理系卒業生を対象に
これから紹介する二択質問に回答してもらい、
回答の傾向が学生と卒業生で異なるかを確認しました。
皆様もその視点で結果を見てください。
*カイ二乗検定などの検定をすることも可能ですが、
回答集団の定義ができていないという背景もあるので、
今回は検定などは実施していません。
何社に応募した?
まずは、就活時に何社に応募したかについて聞き取りました。
今回二択質問にして学生と卒業生の傾向の違いを見たいので、
「10社以下」と「10社より多い」
の二択に回答してもらいました。
現在の学生と卒業生で、応募する会社の数は違うのでしょうか?
結果はこちら↓
この結果を比に直してみると
学生:16.5/28.6 = 0.58
卒業生:18.7/36.3 = 0.52
となり、両者であまり変わらないという結果になりました。
10社を基準に比較した結果という条件付きになりますが、
応募する会社の数については今も昔もあまり変わらないようです。
応募する業界は一つに絞る?複数?
就職活動する際、自分の第一志望の業界しか応募しないという人もいらっしゃると思います。
応募する業界の数を減らすことで、
就活の対策も練りやすくなりますし、
何より行きたい業界へ行ける確率が高くなります。
一方で、業界に強いこだわりがなく、
いろんな業界へ応募する学生も多いと思います。
応募する業界数を広げるか絞るか、
この傾向が今と昔で変わっているかについてアンケートを取りました。
結果はこちら↓
以上の結果を比に直してみると
学生:12.7/29.6 = 0.43
卒業済み:21.1/36.6 = 0.58
となり、昔の方が業界を絞って応募する学生が多かった可能性が見えてきました。
理系就活の情報サイトなどを見ていると
新卒採用で応募できる業界が以前と比べて多くなっているように感じます。
最近の就活生の方が選択肢が多く、いろんな業界に目を向けているのかもしれません。
研究開発系の職種が第一志望?
理系卒、特に修士以上の学生の就活では、
(少なくとも私の時代には)
研究・開発系の職種への応募が王道でした。
先ほど、学生が応募できる職種が今の方が多くなっている傾向がある気がすると述べましたが、
現在でも研究・開発系を志望する学生は多いのでしょうか。
「就職活動での第一志望は研究開発に関する職種ですか?」
というアンケートを、学生と卒業生にとりました。
結果はこちら↓
このような結果となり、研究開発職を目指している(目指していた)人が
現役学生でも卒業生でも多数派であったことが分かりました。
あまり意味はないかもしれませんが、比にした結果も示しておきます。
学生:4.1/39.2 = 0.10
卒業生:8.1/48.6 = 0.17
理系学生の就職希望先として、
企業の研究開発職は依然として優先度の高い選択肢のようです。
インターシップへ参加した?
最後に、インターシップ参加経験について聞き取りました。
就職活動前・活動中にインターンシップへ参加することは、
10年近く前から少しずつ広まり、
現在は多くの理系学生も参加していると聞いています。
そのため、インターンシップへの参加経験については、
今と昔で差がかなりありそうです。
「就職活動でインターンシップへ参加しましたか?」
という質問を、現役学生と卒業生の両方に取りました。
結果はこちら↓
予想通り、現役学生と卒業生で傾向が異なりました。
結果を比に直すまでもなさそうですね。
インターンシップが就活の中で占める割合が増え、
学生側の負担が以前より増えているのが想像されます。
まとめ
・応募する会社の数、業界の数は、現役研究職も学生も大きな違いはない。
・現役研究職も学生も、研究開発職が第一志望の人が多い。
・インターンシップへの参加は、現役学生で多い傾向。
・インターンシップへの参加が増え、学生の負担は現在の方が高そう。
就活は時代とともにルールや戦い方がどんどん変わっているようです。
現在の理系学生の皆様は、直近数年の先輩方の取り組み方を参考に、
ご自身の就活の進め方を考えていくことになると思います。
一方で、目に見えるものも見えないものも含めて、、
就活のルールや常識は毎年少しずつ間違いなく変わっています。
就活を進める際には、正しい情報源から常に情報を集めることが大切です。
特に理系の皆様は理系向けの情報が集まる情報源をうまく利用し、
ご自身の就活の進め方をデザインし、自分らしく進めてもらえればと思います。
理系就活は、理系向け情報が集まるサイトを使おう!
理系就活の進め方を決めるうえで、
理系向けの情報を常に仕入れておくことはとても大切です。
理系学生の就職活動には、
大学院生&理系学生に特化した就活サイト、
アカリクが役立ちます。
最近は、「アカリクイベント」というオンライン就活イベント
以下のリンクから、一度覗いてみて下さい。
アカリクイベントは、こちら
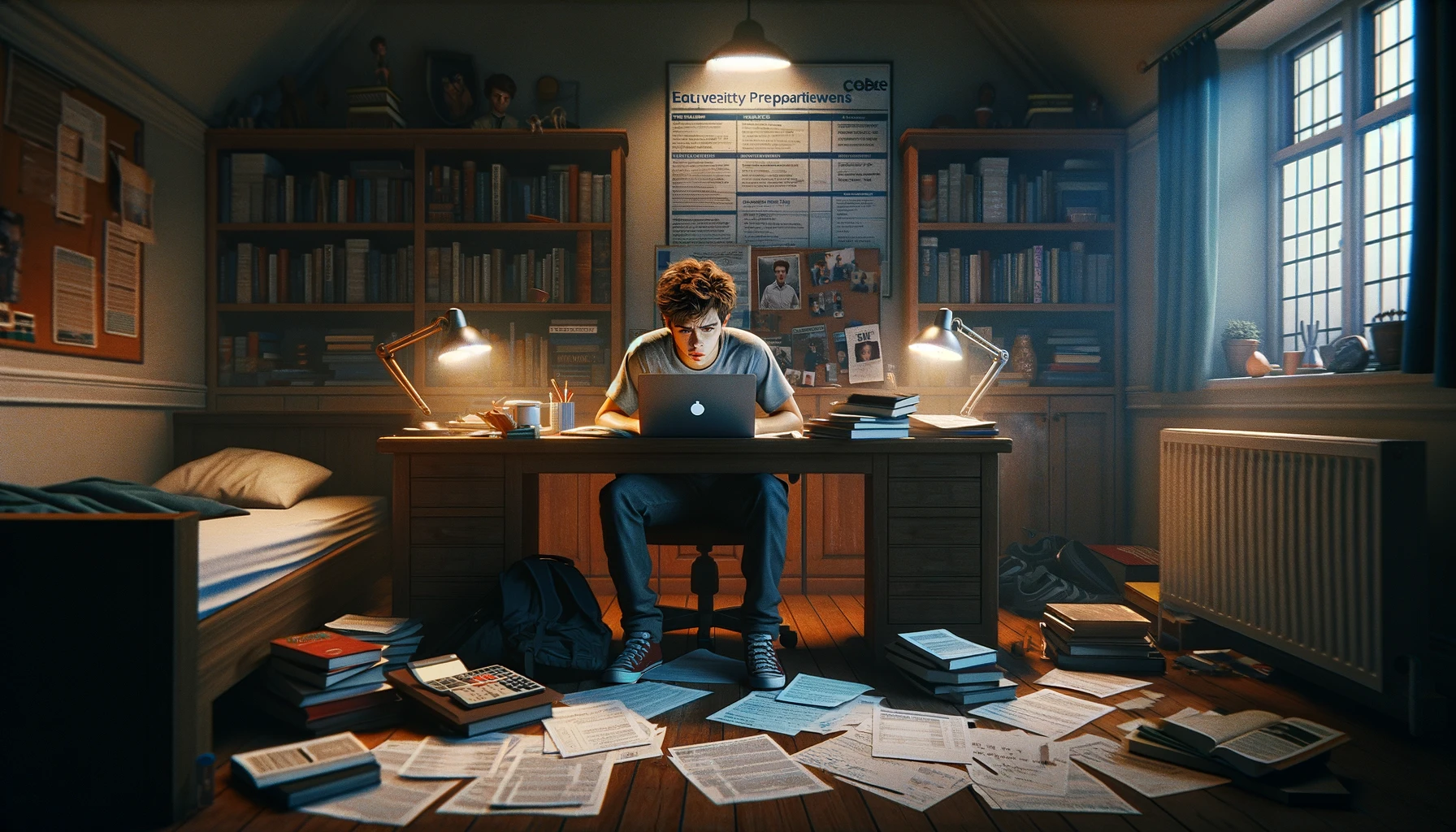








コメント