「研究職を希望しているけど、募集要項に【総合職】と書いている会社でも応募していいの?」
「研究職と総合職って、何が違うの?」
この記事を開いた就活生の皆様、気になりますよね?
理系大学院を卒業される学生の中に、「研究職」を希望されている学生は多いと思います。
研究部門は会社の将来の事業を作る大事な部署であり、所属する研究員は自分の研究が10年20年後に花開くことを目指して日々の業務に励んでいます。
そういったことにやりがいを見出せる方は、ぜひ研究部門に進んでみてください。
しかし、研究職を目指して就職活動をする場合、最初に気を付けなくてはいけないのが
「研究する部署に採用・配属される可能性があるか」を知っておくことです。
特に食品の企業の中には、研究職としての採用枠を設けていない企業が多いです。
現在私は上場企業の研究所で働いています。
しかし、採用時の採用枠は「総合職の理系採用」であり、「研究職」ではありませんでした。
いくつかの部署を巡った後に研究所に配属され、それ以降ずっと研究所で働いています。
採用されたときは必ずしも研究を希望していたわけではなく、様々な巡り合わせを経て今の仕事に辿り着きました。
今回は、
「企業で研究員として働きたいなら、まず「採用枠」を確認しましょう」
という内容についてを書いていきます。
大学院や理系学生の就職活動には、大学院生&理系学生に特化した就活サイト、アカリクが役立ちます。
最近は、「アカリクイベント」というオンライン就活イベントも行われているそうです。
以下のリンクから、一度覗いてみて下さい。
アカリクイベントは、こちら
研究職採用枠があるか確認!ただし、総合職から研究所へ異動するケースもある。
採用枠を確認しましょう。「研究職」なら研究に近い仕事に携われるはず。
就職活動の際に就職四季報や企業のサイトを見ると思いますが、その際「採用枠」もしっかり確認してみましょう。
「研究職」もしくはそれに近い名前の採用枠があれば、研究関連に従事する人を採用枠として確保していることを示しています。
各社の内情までは分かりませんが、採用後は基本的に研究関連部門を中心に配属や異動がなされるようです。
研究職採用のメリット・デメリット
研究職採用のメリットとしては、
研究所が集約されている場合は転居を伴う異動の可能性が低く、ライフプランが立てやすくなるというメリットもあります。
しかしデメリットとして、異動の範囲も研究関連に限定される場合、研究関連の仕事が自分に向いてなかったり楽しくなかったときに、社内でのつぶしが効かなくなる可能性があるようです。
一方、特に食品企業では「研究職」として枠を設けている企業は非常に少ないです。
たいていの場合、「(理系の)総合職」として一括で採用し、その後一部の社員を研究部門へ配属させています。
総合職は「将来の幹部候補であり、それまでは転勤が前提」で採用されています。
配属先も製造、商品開発、品質保証、技術営業、設備管理、情報システムなど多岐にわたり、配属や異動は基本的に会社が決めます。
さまざまな業務に携われるチャンスがあり、自分に合った仕事を見つけられる可能性があります。
自分の意外な長所を見つけられるかもしれません。
総合職採用後に、研究関連部門に異動できる?
さて、総合職採用後に研究関連部門を希望して配属されることはできるのでしょうか。
私の答えとしては、
「可能性はあるが、運や巡り合わせの要素が大きい」となります。
運や巡り合わせというのは、本人がコントロールできない要素が大きく影響するという意味です。
会社の人事異動には、担当者の異動や退職、部署やプロジェクトの新設や廃止などなど、
さまざまな出来事がその都度絡んでいます。
研究員が一度に数人退職したときや、研究プロジェクトが立ち上がるタイミングであれば配属のチャンスは高いかもしれませんが、そうでないときはなかなか難しいかもしれません。
希望の職種にたどり着くには運の要素が大きいですが、その運をつかめるのは普段から準備をしている人です。
配属された部署でしっかり結果を出し、そのうえで配置転換希望を出す、(場合によっては、研究部門の人とつながって顔を覚えてもらう)。
準備をしつつタイミングを逃さないようにしましょう。
研究職と総合職それぞれのメリットデメリット
企業で研究の仕事がしたいという観点での、採用枠ごとメリットデメリットをまとめます。
研究職のメリット、デメリット
・研究に近い分野に携われる可能性が高い。
・特に研究所が集約されている企業であれば、転勤の可能性が総合職と比べて圧倒的に低い。
・実際に仕事をしてみて「なんか違うな…」と思った時に、社内でのつぶしが効きにくい。
・研究以外の分野への配置転換を希望しても、なかなか通らない可能性がある。
総合職のメリット、デメリット
・採用後の配属は会社が決める。転勤を伴う異動が課されることも多い。
・様々な職種に配置される可能性があり、自分に適した意外な仕事を見つけられる可能性がある。
・研究所へ配属されるかは、「運と巡り合わせ」の要素が強く、なかなか難しいこともある。
上記の特徴を踏まえつつ、まずは企業ごとの採用枠や職種を確認してみましょう。
詳細は各企業で異なりますので、同社に就職したOBなどから情報を集めてみてください。
まとめ
・会社ごとに採用の仕方が違うので、採用枠をしっかり確認しよう!
・研究職につきたい場合は、「研究職」と書かれている採用枠の方が、研究関連の仕事に就ける可能性が高い。
・「研究職」「総合職」それぞれに特徴があります。自分が進みたい道やなりたい姿をイメージしたうえで選考にエントリーしましょう。
今後も定期的に就活関連の記事を作成していきます。
理系就活をする際は、理系向け情報が集まるサイトを使おう!
この記事を読んでいる中に理系就活を準備している人がいましたら、とてもうれしいです。
ぜひ皆様には納得できる就職活動を過ごしてほしいですし、記事を書くことで少しでもその応援ができればと思います。
理系向けの就活情報をうまく使い、自分らしく就職活動を進めてみてください。
また、理系就活では、理系向けの情報を常に仕入れておくことはとても大切です。
理系学生の就職活動には、
大学院生&理系学生に特化した就活サイト、
アカリクが役立ちます。
最近は、「アカリクイベント」というオンライン就活イベントも行われているそうです。
以下のリンクから、一度覗いてみて下さい。
アカリクイベントは、こちら
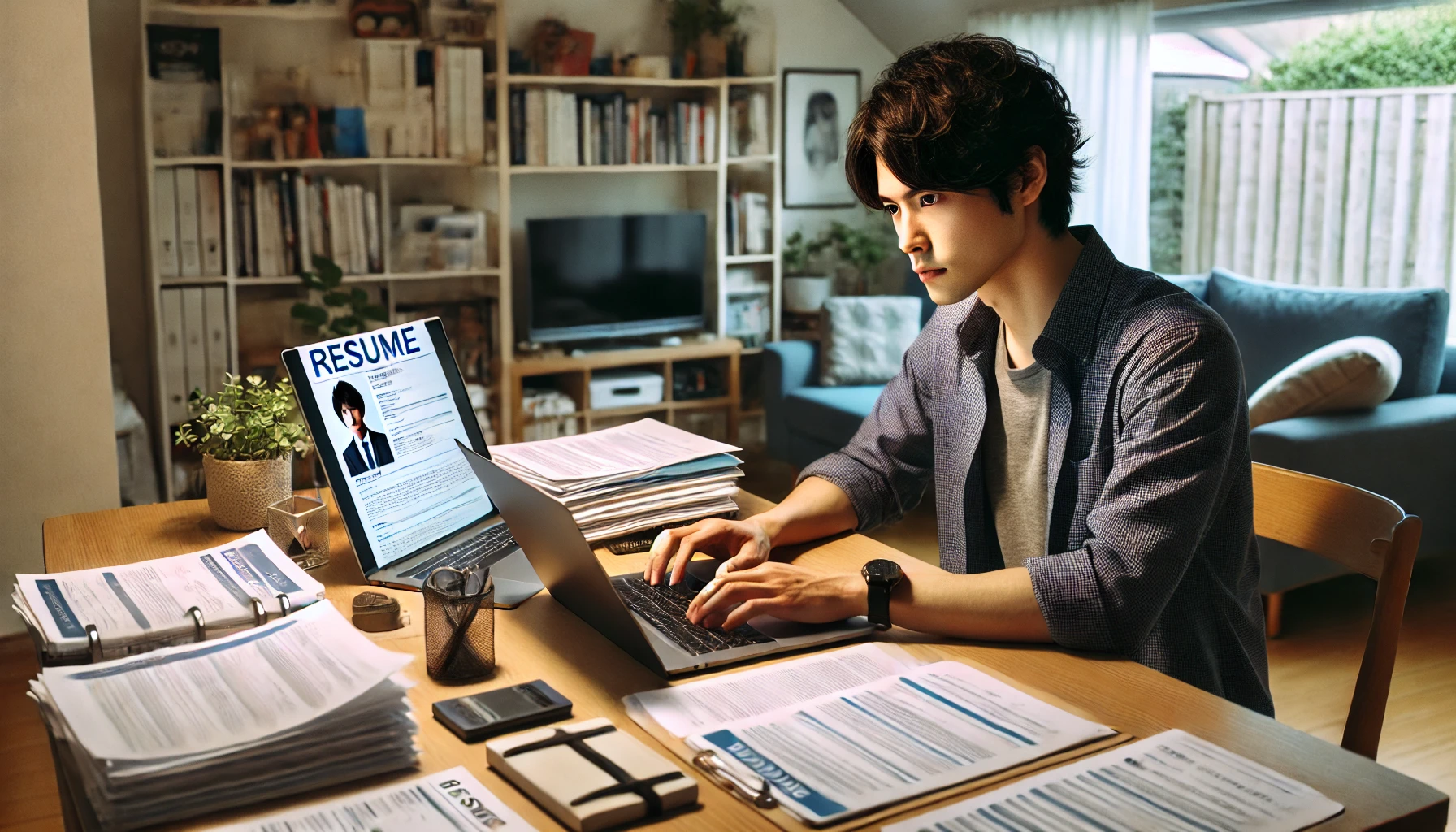








コメント